午後の紅茶の世界へようこそ!今日は日本を代表する紅茶飲料「午後の紅茶」についてご紹介したいと思います。この飲み物、実はとても奥が深いんですよ。
ペットボトルの紅茶といえば「午後の紅茶」と言われるほど、私たちの生活に根付いた存在になっていますよね。どこのコンビニでも見かける親しみやすいあのボトル。でも、あの飲み物について、あなたはどれだけ知っていますか?
- 午後の紅茶は1986年から販売されている国民的紅茶飲料
- 名前の由来はイギリスの伝統的な「アフタヌーンティー」から
- 多彩なラインナップで様々な味わいを楽しめる人気商品
今回の記事では、午後の紅茶にまつわる豊かな物語と、知っておくと楽しい情報をたっぷりとお届けします。知れば知るほど、次に飲むときの味わいが変わるかもしれませんよ。それでは、午後の紅茶の魅力に一緒に浸っていきましょう!
午後の紅茶を作っている会社

皆さんが日常的に手に取る「午後の紅茶」、実はどこの会社が作っているか知っていますか?さすがに誰でも知ってそうですが、意外と知らない人も多いみたいですね。
キリンビバレッジの看板商品
午後の紅茶は、キリンビバレッジ株式会社によって製造されています。キリンというと、ビールのイメージが強いかもしれませんが、実は清涼飲料事業も大きな柱なんですよ。
キリンビバレッジは、もともとキリンホールディングス(旧・麒麟麦酒)のグループ会社として1963年に設立されました。現在は清涼飲料事業を担当する完全子会社として運営されています。
キリンビバレッジの事業内容
キリンビバレッジは午後の紅茶だけでなく、以下のような主力商品を展開しています。
- 緑茶飲料「生茶」
- 缶コーヒー「ファイア」
- プラズマ乳酸菌入り飲料「キリン おいしい免疫ケア」
キリンビバレッジの事業戦略としては、基盤ブランドの再成長とヘルスサイエンス飲料の拡充を通じて、高収益化を目指しています。特に近年は健康志向の高まりを受けて、機能性飲料の開発にも力を入れているようです。
私が最近注目しているのは、彼らの環境への取り組みです。午後の紅茶でも再生ペット樹脂を100%使用した「R100ペットボトル」を導入するなど、サステナビリティにも力を入れています。飲料メーカーとしての責任を果たす姿勢には感心しますね。
キリンビバレッジの企業理念
キリンビバレッジは「自然と人を見つめるものづくりで、『食と健康』の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献する」という企業理念を掲げています。
この理念は、同社の商品開発にも反映されています。例えば、午後の紅茶では茶葉の選定から製法までこだわり抜いて、本格的な紅茶の味わいを追求しています。
私が業界内の交流会で聞いた話では、キリンビバレッジは社員の方々が自社商品に対して本当に愛着を持っているそうです。そんな想いが、長年愛され続ける商品づくりにつながっているのかもしれませんね。企業文化って、実は製品の味にも影響するものなんだなと感じています。
午後の紅茶はいつからある?
「午後の紅茶って、実はいつから販売されているの?」と疑問に思ったことはありませんか?私も以前、この質問を友人から受けて調べたことがあります。意外と知られていない午後の紅茶の誕生秘話をご紹介しましょう。
午後の紅茶の誕生日
午後の紅茶は1986年10月13日に初めて発売されました。つまり、もう30年以上も日本人に愛され続けている長寿商品なんです。
最初に登場したのは1.5リットルのペットボトル入り紅茶飲料でした。これは当時としては革新的な商品でした。なぜなら、それまで紅茶は缶入りか瓶入りが主流だったからです。
私が子どもの頃を思い出すと、確かにペットボトル入りの飲料が増え始めた時期でした。午後の紅茶はその先駆けだったんですね。飲料業界の転換期を作った商品の一つといえるでしょう。
クリアアイスティー製法の革新性
午後の紅茶が画期的だったのは、「クリアアイスティー製法」という独自技術を用いていたことです。この製法により、冷やしても白く濁らない透明感のある紅茶を実現しました。
当時、紅茶飲料の多くは冷やすと濁ってしまうのが一般的でした。しかし、午後の紅茶は透明感を保ったまま本格的な紅茶の味わいを提供できたのです。これが多くの消費者の心を掴んだ理由の一つだったようです。
この技術開発の裏話を業界セミナーで聞いたことがありますが、開発者たちは何度も試行錯誤を重ねたそうです。飲料開発って、ちょっとした科学実験のようで面白いですよね。
ブランドの成長と進化
発売から現在に至るまで、午後の紅茶は常に進化し続けています。最初はストレートティーだけでしたが、その後ミルクティーやレモンティーなどのバリエーションが追加されていきました。
また、パッケージデザインもたびたびリニューアルされてきました。私のコレクション趣味からか、過去のパッケージを見ると当時の流行やデザイントレンドが反映されていて興味深いです。
近年では環境に配慮した「ペコロジーボトル」の採用など、時代のニーズに合わせた取り組みも行っています。歴史を重ねながらも常に新しい挑戦を続ける姿勢は、長く愛される秘訣かもしれませんね。
私が飲料業界で学んだのは、愛されるブランドになるためには「変わらない価値」と「変化への適応」の両方が必要だということ。午後の紅茶はその好例といえるでしょう。伝統と革新のバランス。紅茶の味わいそのものです。
午後の紅茶の名前の由来
ふと気になったことはありませんか?「なぜ『午後の紅茶』というネーミングなんだろう?」と。私も実は以前から興味があったのですが、その由来にはイギリスの上品な文化が関わっていたんです。
イギリスのアフタヌーンティー文化
午後の紅茶の名前は、イギリスの伝統的な「アフタヌーンティー」に由来しています。「afternoon(午後)」と「tea(紅茶)」を直訳したものなんですね。
アフタヌーンティーとは、19世紀中頃に第7代ベッドフォード公爵夫人アンナ・マリア・ラッセルが始めたとされる習慣です。午後4時頃に紅茶と軽食を楽しむ優雅な社交の場として、上流社会に広まりました。
私がイギリスを訪れた際、本場のアフタヌーンティーを体験しましたが、その優雅な雰囲気はまさに「文化」そのものでした。サンドイッチやスコーン、ケーキなどの軽食とともに楽しむ紅茶の時間は、まさに「午後の贅沢」です。
日本への紅茶文化の普及への願い
興味深いのは、この名前には「日本にも紅茶の本場イギリスの習慣を根付かせたい」という願いが込められていたことです。単なる商品名ではなく、文化の普及という使命を帯びていたわけです。
1986年当時の日本では、缶コーヒーなどは普及していましたが、紅茶飲料はまだメジャーではありませんでした。そんな中で、本格的な紅茶文化を気軽に味わえる商品として「午後の紅茶」は誕生したのです。
私が飲料業界に入った頃、先輩から聞いた話では、開発当初は「午前の紅茶」という案もあったそうです。でも、イギリスのアフタヌーンティーの文化を反映させるという意図から「午後の紅茶」に決まったとか。ネーミングって本当に奥が深いですね。
商品ロゴのこだわり
商品のロゴにも、このような文化的背景が反映されています。午後の紅茶のパッケージに描かれている女性のシルエットは、アフタヌーンティーの始まりに関わったアンナ・マリア・ラッセル夫人がモデルとされています。
このロゴデザインには、本格的な紅茶のイメージを視覚的に表現する意図があったんですね。私は昔からこのシルエットが印象的で、見かけるとなんだか優雅な気分になりました。
このように、午後の紅茶のネーミングからロゴデザインまで、すべてにイギリスの紅茶文化への敬意と、その普及への願いが込められているんです。単なる飲み物ではなく、文化を伝える媒体としての役割も果たしてきたわけですね。
飲料のブランディングにおいて、名前とデザインの力は計り知れません。私の経験上、消費者は無意識のうちにそれらから様々なメッセージを受け取っています。午後の紅茶の成功は、その名前が持つ文化的な響きもあったからこそなのかもしれません。奥深い。
午後の紅茶の商品種類(ラインナップ)

コンビニや自販機で見かける午後の紅茶ですが、実は種類が豊富なことをご存知ですか?私もスーパーで新商品を見つけるたびにワクワクしてしまいます。それでは、午後の紅茶の多彩なラインナップを詳しく見ていきましょう。
レギュラーシリーズの定番商品
午後の紅茶といえば、まず思い浮かぶのがレギュラーシリーズの3種類ですよね。
- ストレートティー:華やかな香りと心地よい渋みが特徴のアイスストレートティー
- ミルクティー:まろやかでクリーミーなテイストのミルクティー
- レモンティー:程よい酸味のあるレモン風味の紅茶
これらは発売以来のロングセラー商品です。私が学生の頃から変わらない味わいで、いつ飲んでも安心感があります。特にミルクティーは、濃厚なのにゴクゴク飲めるバランスが絶妙ですよね。茶葉の香りとミルクのまろやかさが絶妙に調和しています。
実は以前、メーカーの方に「なぜこの3種類が定番になったのか」と尋ねたことがあります。答えは「日本人の好みに合わせて、基本的な紅茶の楽しみ方をカバーしたから」とのこと。シンプルながら奥深い回答でした。
TEA SELECTIONシリーズの特徴
定番商品に加えて、より本格的な紅茶体験を提供する「TEA SELECTION」シリーズも展開されています。
- ロイヤルブレンドティーラテ:芳醇な香りのブレンドティーにミルクを加えたラテスタイル
- チャイティーラテ:スパイスが効いたチャイをベースにしたティーラテ
- チョコレートティーラテ:甘さと風味が楽しめるチョコレート味の茶飲料
- アップルティープラス:フルーティーなアップル風味が追加された紅茶
このシリーズは、より専門的な紅茶の世界を気軽に楽しめるようにしたものです。私はチャイティーラテが特に好きで、あのスパイシーな香りにホッとする瞬間があります。
紅茶好きの友人に「TEA SELECTION」シリーズを勧めると、「これペットボトルなの?」と驚かれることも。それくらい本格的な味わいを実現しているんですよね。
おいしい無糖シリーズの魅力
健康志向の高まりを受けて人気なのが「おいしい無糖」シリーズです。
- おいしい無糖 ミルクティー:無糖でありながらもミルク感を大切にした製品
- おいしい無糖 香るレモン:レモンエキスを加えた無糖紅茶
このシリーズは、糖質を気にする方でも紅茶の風味を楽しめるように開発されました。私の周りでも、ダイエット中だけど午後の紅茶が飲みたい!という声をよく聞きます。そんな方には、このシリーズはまさに救世主ですよね。
特筆すべきは、「無糖なのにおいしい」という点。砂糖なしでも飲みやすく仕上げるのは実は大変なことなんです。私も飲料開発に携わったことがありますが、甘さなしで満足感を出すのは高度な技術が必要です。
季節限定商品の楽しみ
午後の紅茶の楽しみの一つが、季節限定商品です。例えば:
- 芳醇白桃ティーソーダ(夏限定)
- 熊本県産いちごティー(冬限定)
- 季節のご褒美フルーツティー(季節ごとに変わる)
これらの商品は、その季節の旬の果物の風味を活かした特別なブレンドです。私は毎年、「今年はどんな季節限定が出るんだろう?」とワクワクします。
季節限定商品のリリース情報をチェックするのが趣味になっている友人もいるほど、マニアックなファンも多いんですよ。限定品の醍醐味ですね。
午後の紅茶は、基本の味わいを大切にしながらも、常に新しい提案を続けているブランドです。これからも新たなラインナップが登場することを期待しています。多様性。紅茶の楽しみ方も人それぞれ。だからこそ、選べる幸せがあるんですね。
午後の紅茶の人気ランキング
「午後の紅茶の中で一番人気なのはどれ?」そんな疑問を持ったことはありませんか?私も飲料のトレンドウォッチャーとして、常に注目しています。それでは、午後の紅茶の人気ランキングに迫っていきましょう。
定番商品の人気度
まず、定番商品の人気ランキングをご紹介します。これは実際の販売データに基づいたものです。
- KIRIN 午後の紅茶 ミルクティー:断トツの1位を誇る看板商品
- KIRIN 午後の紅茶 レモンティー:爽やかさが人気で特に夏場に支持が高い
- KIRIN 午後の紅茶 ストレートティー:紅茶本来の味を楽しむ人に支持される
- KIRIN 午後の紅茶 おいしい無糖:健康志向の高まりで近年急速に人気上昇
ミルクティーが不動の1位というのは、多くの方の予想通りかもしれませんね。あの濃厚でクリーミーな味わいは、日本人の口に合うようです。私も疲れた時につい手が伸びるのはミルクティーです。
実はある販売データによると、ミルクティーとレモンティーの販売比率は季節によって変動するそうです。夏場はレモンティーの爽やかさが人気を集め、冬場はミルクティーの温かみを感じる味わいがより支持されるとか。季節感と味の相性って面白いですよね。
プレミアムライン・特別商品の人気
一般的なランキングには表れにくい、プレミアムラインや特別商品の人気も無視できません。
- KIRIN 午後の紅茶 芳醇 ロイヤルミルクティー:プレミアム感が好評
- KIRIN 午後の紅茶 ザ・マイスターズ ミルクティー:専門家監修の本格派
- KIRIN 午後の紅茶 エスプレッソ ティーラテ:珍しい組み合わせが話題に
これらの商品は、一般のランキングではミルクティーやレモンティーほどの数字は出せませんが、コアなファンを獲得しています。私もザ・マイスターズシリーズは特別な日に飲むご褒美として楽しんでいます。
業界内では「ニッチな商品でも固定ファンを持つことがブランド力につながる」と言われていますが、午後の紅茶はそのバランスが絶妙ですね。
年代別の人気傾向
興味深いのは、年代によって支持される商品が異なる点です。
- 若年層(10代~20代):フルーツティーやソーダ系の甘みのある商品が人気
- 中年層(30代~40代):ミルクティーやレモンティーなど定番商品が支持される
- シニア層(50代以上):無糖やストレートなど、すっきりした味わいが好まれる
この傾向からは、日本人の味覚の変化も垣間見えます。私が業界のデータ分析をしていた時に気づいたのですが、年齢を重ねるにつれて甘さへの嗜好が変化する傾向があるんですよね。
もちろん個人差はありますが、このようなデータは商品開発の重要な指針になっています。キリンビバレッジもきっと、各年代のニーズを細かく分析しているのでしょう。
地域別の人気差
意外と知られていないのが、地域によって人気商品が異なる点です。例えば:
- 北海道・東北:ホット向け商品の支持率が高い
- 関東:バラエティ豊かな消費傾向で新商品の試飲率も高い
- 関西:レモンティーが特に人気
- 九州・沖縄:フルーティーな商品が好まれる傾向
私は仕事で各地を回ることが多いのですが、確かにコンビニの棚を見ると地域ごとに置いてある商品の比率が微妙に異なるんです。これは気候や食文化の違いも影響しているのでしょうね。
ランキングはあくまで全体の傾向であり、一人ひとりの好みは十人十色です。あなたのお気に入りは定番のミルクティーですか?それとも別の味わい?次に午後の紅茶を手に取る時、ちょっと違う種類を試してみるのも楽しいかもしれませんね。意外な発見があるかも。
午後の紅茶のカフェイン量
午後の紅茶を飲むとき、「今日はもう夜だけど、カフェインは大丈夫かな?」って思ったことありませんか?私も夜にゴクゴク飲んでしまって、後から「あ、これカフェイン入ってたんだ…」と気づいて後悔したことがあります。
午後の紅茶はその名の通り紅茶飲料なので、もちろんカフェインが含まれています。でも、実は商品によってその量がかなり違うんですよ。意外と知られていない事実。
午後の紅茶の商品別カフェイン含有量
午後の紅茶の主要商品のカフェイン量を見てみましょう。500mlペットボトル1本あたりの含有量です。
- ストレートティー:約70mg
- ミルクティー:約100~105mg
- レモンティー:約45mg
- おいしい無糖:約55mg
- カフェインゼロ ピーチティー:0mg(カフェインフリー)
驚きじゃないですか?同じ午後の紅茶なのに、ミルクティーとレモンティーでは2倍以上カフェイン量が違うんです。これは茶葉の使用量や種類によって変わってくるんですね。
ちなみに、コーヒー1杯(約200ml)のカフェイン量が約60~80mgと言われているので、午後の紅茶ミルクティー500mlを飲むと、コーヒー1杯半分くらいのカフェインを摂取することになります。
午後の紅茶の砂糖の量

甘くて美味しい午後の紅茶ですが、実は砂糖がかなり含まれているのをご存知でしたか?私も最初に知ったときは「え、こんなに入ってるの?」と驚きました。
各フレーバーの砂糖含有量
午後の紅茶の各フレーバーの砂糖(糖質)含有量を500mlペットボトル1本あたりで見てみましょう。
| 商品名 | 糖質量 | 角砂糖換算 |
|---|---|---|
| ストレートティー | 約20g | 約6個分 |
| ミルクティー | 約39g | 約12個分 |
| レモンティー | 約35g | 約11個分 |
ミルクティー1本で角砂糖約12個分というのは、想像以上じゃないですか?これは一度の食事で摂取する量としては決して少なくないんです。
無糖シリーズの登場
こうした健康意識の高まりから、キリンビバレッジは「午後の紅茶 おいしい無糖」シリーズを展開しています。砂糖を気にする方にはこちらがおすすめ。
私個人としては、味の好みもありますが、砂糖の量を意識するようになってからは「おいしい無糖」シリーズを選ぶことが増えました。紅茶本来の風味を楽しめるのも魅力です。
午後の紅茶は本物の紅茶の茶葉を使っている?

「午後の紅茶って本当に紅茶葉から作ってるの?それとも香料とかで味付けしてるだけなの?」こんな疑問を持ったことはありませんか?私も昔、ペットボトル飲料は「まがい物」なんじゃないかと思っていた時期がありました。でも、調べてみると、午後の紅茶は本物にこだわっているんですよ。
使用されている茶葉
午後の紅茶は、確かに本物の紅茶の茶葉を使用しています。特に、スリランカ産のセイロンティーを中心に使った製品が多いんです。1986年の発売以来、午後の紅茶は「日本初の本格ペットボトル紅茶」として市場に登場しました。
毎年、スリランカから約2,000トンものセイロンティーを輸入して使用しているそうです。これは日本の紅茶葉輸入総量の中でもかなりの割合を占めているんですよ。
茶葉の種類と選定基準
午後の紅茶では、製品ごとに異なる茶葉をブレンドして使用しています。例えば:
- ディンブラ:香り高く、さわやかな味わい
- ヌワラエリヤ:高地で栽培される上質な茶葉
- キャンディ:ミルクとの相性が良い茶葉
- ダージリン:インド産の上質な茶葉
- アッサム:コクのある味わいの茶葉
これらの茶葉は、それぞれ特有の香りや渋みを持っており、午後の紅茶の商品ごとに最適なブレンドで使用されているんです。「マイクロ・ブリュー製法」という独自の抽出方法で、茶葉本来の風味を最大限に引き出しているそうです。
サスティナブルな取り組み
さらに、キリンビバレッジはスリランカ産茶葉の持続可能な生産を支援しています。レインフォレスト・アライアンス認証を取得した農園から茶葉を調達するなど、環境保護や品質向上にも取り組んでいます。
私がこれを知ったとき、「ただの飲み物」と思っていた午後の紅茶に対する見方が変わりました。本物の茶葉へのこだわりと、生産地への配慮。そんな背景があるからこそ、あの味わいが生まれるんですね。
午後の紅茶のミルクティーは牛乳を使っている?
「午後の紅茶のミルクティーって、本当に牛乳が入ってるの?それとも乳風味の香料とかなのかな?」と疑問に思ったことはありませんか?ペットボトル飲料だから何か別のものを使っているんじゃ…という疑いを持つのも自然なことだと思います。私も気になって調べてみました。
原材料の真実
結論から言うと、午後の紅茶のミルクティーには本物の牛乳が使われています。しかも「生乳(国産)」と表示されているように、日本産の生乳が使用されているんです。
具体的に「午後の紅茶 ミルクティー」の主な原材料は:
- 牛乳(生乳(国産))
- 砂糖
- 紅茶(キャンディ茶葉を約20%含む)
これらの原材料を見ると、本物の牛乳と本物の紅茶葉を使った本格的なミルクティーだということがわかります。その証拠に、開封した瞬間の香りは本物のミルクティーそのもの。
おいしい無糖ミルクティーの場合
「午後の紅茶 おいしい無糖 ミルクティー」の場合も同様に、牛乳(生乳(国産))が使われています。紅茶葉には、ダージリンとウバをそれぞれ10%使用しているそうです。
この商品は、環境に配慮した「R100ペットボトル」という再生ペット樹脂を100%使用したボトルに入っており、味だけでなく環境への配慮も感じられる製品になっています。
ミルクティーのクリーミーさの秘密
午後の紅茶のミルクティーが特にクリーミーな味わいを持っているのは、この本物の牛乳を使っているからこそ。紅茶葉の選定にも工夫があり、特にミルクティーには「キャンディ」という茶葉を20%も使用しているそうです。この茶葉はミルクとの相性が良く、豊かな香りと濃厚な味わいを楽しめるよう選ばれています。
私は長年ミルクティー派なのですが、その美味しさの秘密を知って納得。本物の材料を使っているからこそ、あの満足感のある味わいが生まれるんですね。
午後の紅茶のホットとアイスでは味が違う?
「午後の紅茶」には通常の「アイス用」と「ホット専用」の商品がありますよね。私は長年「同じでしょ?」と思ってたんですが、実はかなり違うんです。この違いを知って、より楽しく午後の紅茶を味わえるようになりました。
味の違いの要因
ホットとアイスで味が違う主な理由はこれ。
- 茶葉のブレンドと製法の違い
- 温度による風味の変化
- 商品設計そのものの違い
特に重要なのは、ホット専用商品は温かい状態で美味しく感じられるように設計されているという点です。茶葉のブレンドや甘さ、濃さ、香り立ちが温かいときに最適になるよう調整されているんですよ。
逆に、アイス用は冷やした状態で風味が際立つよう作られています。
体験的な味の違い
実際に飲み比べた印象をお伝えすると:
| タイプ | 味わいの特徴 |
|---|---|
| アイス | 茶葉の風味が強く、苦味も感じられる。後味がすっきりして、紅茶本来の味わいを楽しめる |
| ホット | 香りが柔らかく、ミルクや甘さが前面に出る。デザート感覚で楽しめる甘さが特徴的 |
温めると香りが立ち、ミルク感や甘さが強調される傾向があるんですね。反対に、冷たい状態では茶葉の苦味や濃厚な風味がより感じられます。
パッケージの違い
見た目でも区別できるように、ホット用とアイス用ではパッケージデザインも異なります。ホット用は通常オレンジ色のキャップ、アイス用は青色のキャップが特徴的です。
また、ホット用のペットボトルは耐熱設計になっていて、電子レンジでの加熱が可能です。アイス用は耐熱性がないので、温めることはできません。
私はこの違いを知ってから、季節やシチュエーションに合わせて使い分けるようになりました。冬の寒い日には濃厚な「ホット専用」を温めて飲み、暑い夏の日中には「アイス用」を冷やして楽しむ。それぞれの良さを知ることで、午後の紅茶の楽しみ方が広がりましたよ。
午後の紅茶は海外でも売られている?
「午後の紅茶って日本だけの飲み物なの?」と疑問に思ったことはありませんか?私は海外旅行に行くたびに、つい現地のスーパーやコンビニで探してしまうんです。結論から言うと、午後の紅茶は実は一部の国で販売されているんですよ。
海外展開している地域
午後の紅茶が公式に販売されている主な国・地域は以下の通りです:
- 中国(2001年から「午后红茶」として販売)
- 台湾(2001年から「午後の紅茶」として販売)
- 香港
- タイ(2009年から「午後の紅茶 Tea Break」として販売)
- 韓国(一部のコンビニエンスストアで販売情報あり)
特に中国語圏では「午后红茶」という名前で親しまれているんですね。海外で見かけた日本人観光客が「日本と同じだ!」と喜んで買っていく光景もよく見られるそうです。
海外での人気度
海外での午後の紅茶の味は、基本的に日本のものと同様だという報告があります。ただ、地域によって特に人気のあるフレーバーは異なるようです。例えば、アジア地域ではミルクティー味が特に人気があると言われています。
アメリカなどでは日系スーパーで時折販売されることがあり、日本食品を求める在住の日本人や日本文化ファンに人気があるようです。ただし、公式な販売地域ではないため、入手は限定的です。
文化の違いと受け入れられ方
興味深いのは、各国での「紅茶文化」の違いによって、午後の紅茶の受け止められ方が少し異なるという点です。例えば、英国のような紅茶文化が深い国では「ペットボトルの紅茶」という概念が馴染みにくい面もあるかもしれません。
一方で、アジア地域では手軽に飲める紅茶飲料として受け入れられているようです。特にティーブレイクの文化がある国々では、その名前の由来とコンセプトも理解されやすいのかもしれませんね。
私は台湾旅行中に現地のコンビニで午後の紅茶を見つけたときは、思わず「懐かしい!」と感じました。海外で日本のおなじみの味に出会うと、なぜかホッとするものですね。
午後の紅茶の賞味期限
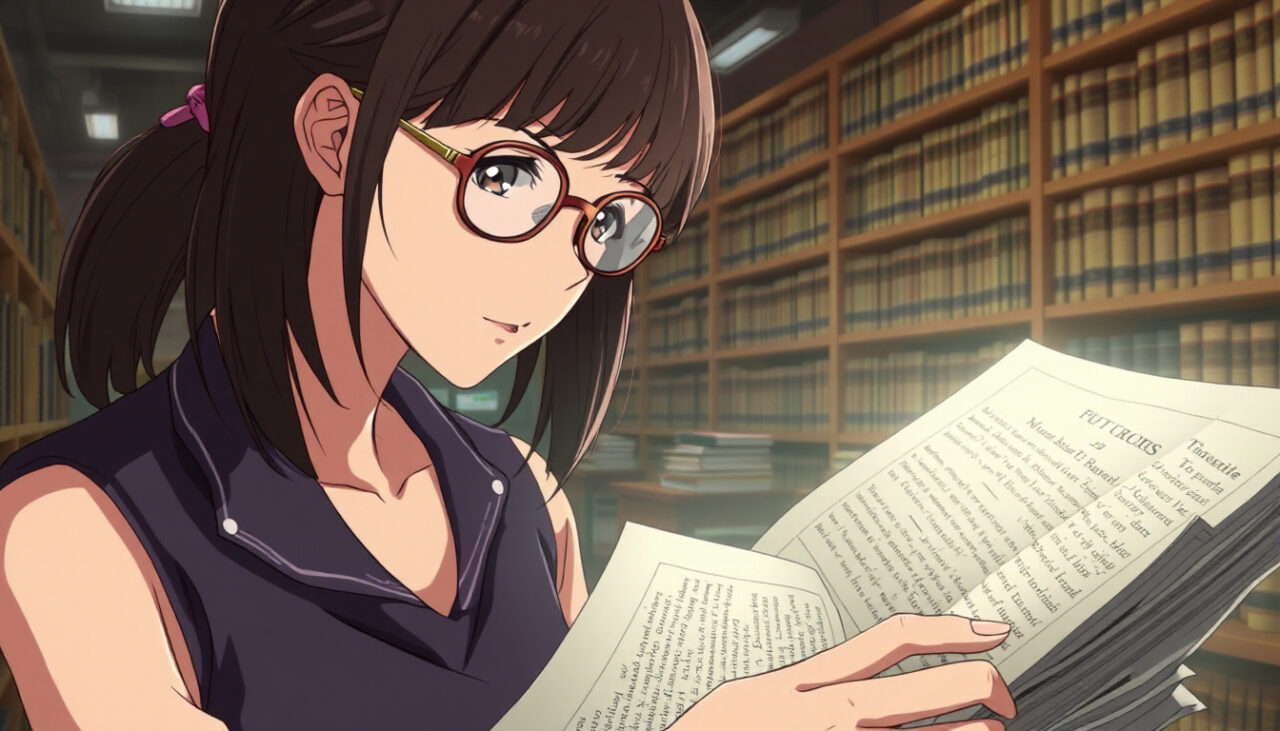
「午後の紅茶をまとめ買いしたけど、賞味期限はどれくらいあるんだろう?」と気になったことはありませんか?私もセールのときについ箱買いしてしまうので、保存可能期間は気になるポイントです。
商品タイプ別の賞味期限
午後の紅茶の賞味期限は、商品によって異なります。主な商品の賞味期間は以下の通りです:
| 商品名 | 賞味期間 |
|---|---|
| 午後の紅茶 ストレートティー 500mlペットボトル | 12ヶ月 |
| 午後の紅茶 ミルクティー 500mlペットボトル | 12ヶ月 |
| 午後の紅茶 レモンティー 500mlペットボトル | 9ヶ月 |
| 午後の紅茶 おいしい無糖 500mlペットボトル | 9ヶ月 |
基本的に未開封の状態で9〜12ヶ月の賞味期間があるため、まとめ買いしても比較的長く保存できます。ただし、これは適切な保存状態を前提としています。
適切な保存方法
午後の紅茶を長持ちさせるためには、以下のような保存方法がおすすめです:
- 直射日光を避ける
- 高温多湿の場所を避ける
- 強い衝撃を与えない
- 開封後は冷蔵庫で保管し、なるべく早く飲みきる
特に夏場は気温が高くなるため、直射日光の当たらない涼しい場所での保管が重要です。車内など高温になる場所に長時間放置するのも避けたほうが良いでしょう。
開封後の注意点
午後の紅茶は、開封後は品質が急速に変化する可能性があります。開封したら冷蔵庫で保管し、できるだけ2〜3日以内に飲み切るのがベストです。
私の経験では、特にミルクティーは開封後の変化が早く、風味が落ちやすいように感じます。一度開けたら、その日のうちに飲み切るか、翌日には飲み切るようにしています。
また、開封後のペットボトルは密閉性が低下しているため、他の食品の匂いを吸収する場合もあります。冷蔵庫で保管する際は、強い香りの食品と離して置くといいでしょう。
午後の紅茶の基本情報のまとめ
午後の紅茶について、たくさんの情報をご紹介してきましたが、いかがでしたか?私自身、調べれば調べるほど「こんなに奥が深いんだ!」と驚かされました。最後に、ここまでの内容を振り返っておさらいしましょう。
午後の紅茶は、キリンビバレッジによって1986年に誕生した日本を代表する紅茶飲料です。イギリスのアフタヌーンティー文化から名付けられ、本物の紅茶葉を使用した本格的な飲み物として愛され続けています。
ここで重要なポイントをまとめると
- カフェイン量は商品によって異なり、特にミルクティーは約100mg以上と多め
- 砂糖量もフレーバーによって差があり、ミルクティーは500mlで角砂糖約12個分
- 本物のスリランカ産セイロンティーなど厳選された茶葉を使用
- ミルクティーには本物の国産牛乳を使用している
- ホット専用とアイス用で味や設計が異なる
- 中国、台湾、タイなど一部のアジア地域で海外展開している
- 未開封の賞味期限は9〜12ヶ月と比較的長い
私たちが何気なく飲んでいる午後の紅茶ですが、その背景には茶葉へのこだわりや製法の工夫があることがわかりました。また、健康志向に合わせた「おいしい無糖」シリーズや、環境に配慮した取り組みなど、時代とともに進化し続けている点も印象的です。
これからも私たちの日常に寄り添い続ける午後の紅茶。この記事を読んだ後に飲む一杯は、きっといつもより深い味わいに感じられるのではないでしょうか。「午後の紅茶の基本情報」をご紹介しましたが、ぜひお気に入りのフレーバーを見つけて、その豊かな味わいを楽しんでみてくださいね。


コメント